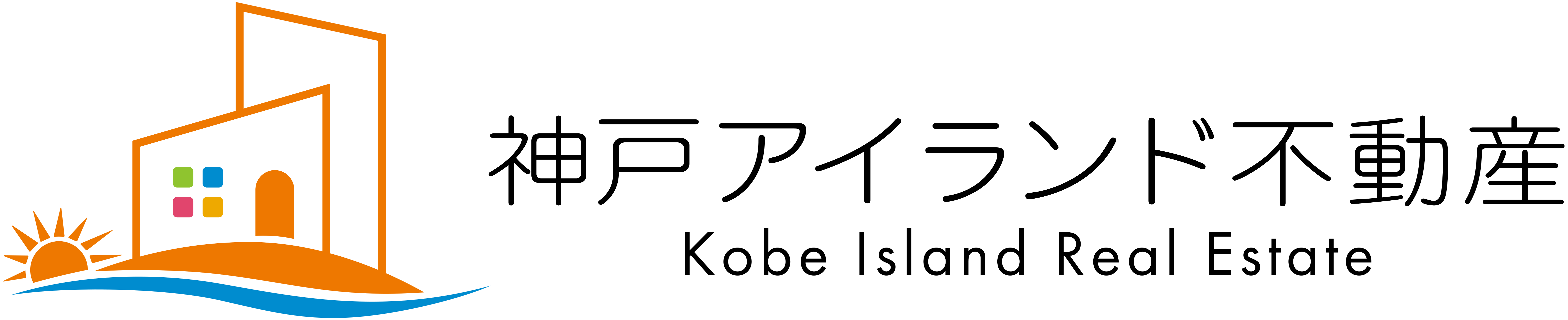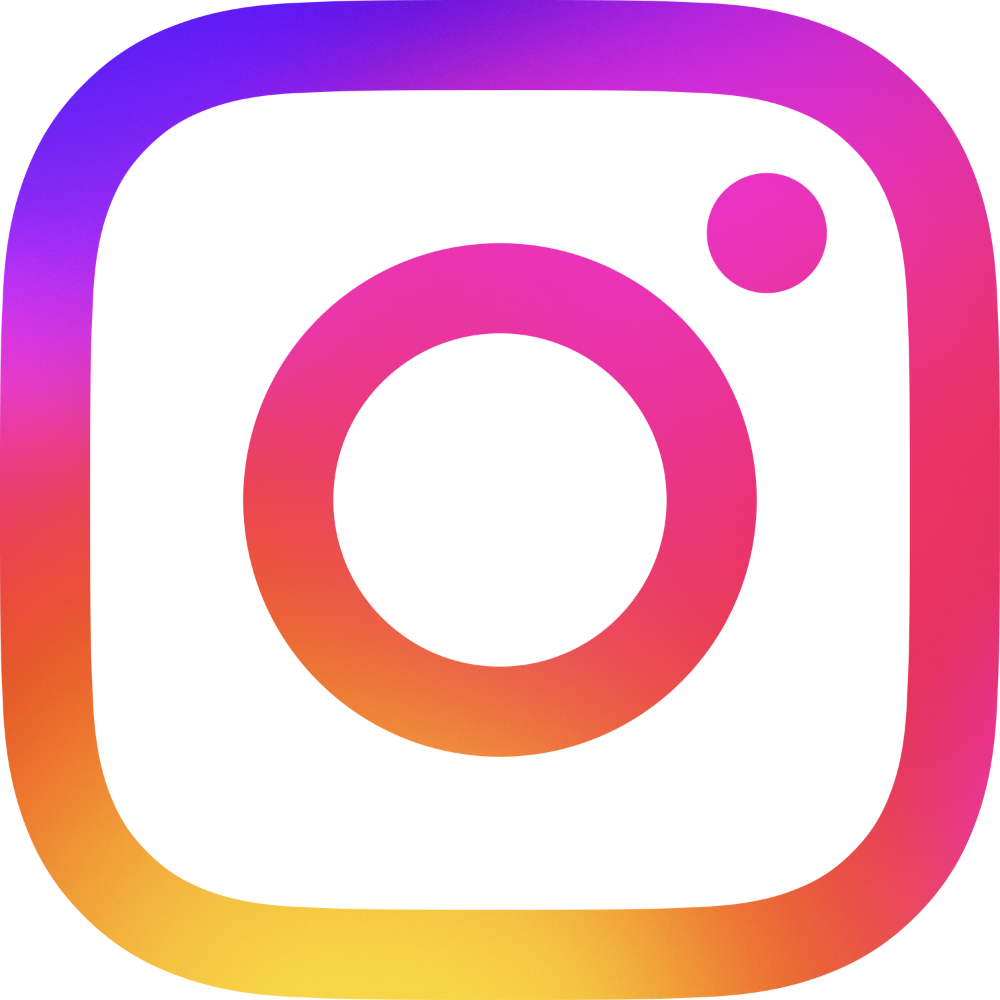令和6年路線価は関西も軒並み上昇
国税庁は7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる土地の路線価(2024年1月1日時点)を公表した。
標準宅地の評価基準額は全国平均2.3%上昇し、3年連続で上昇。全国平均は前年の1.5%上昇から0.8ポイント拡大しました。
評価対象は、宅地に係る標準値は約32万か所です。価格は国土交通省が毎年発表している地価公示価格水準の80%程度が目安となります。
国税庁が不動産の売買取引事例や不動産鑑定士の意見などを参考にして算出される路線価。
相続税などの申告で土地の時価を把握する算定基準の一つとするよう定めています。
都道府県別に評価基準額の対前年変動率の平均値で最も上昇率を上げたのは福岡県の5.8%、2位が沖縄県(5.6%)、3位が東京都(5.3%)となりました。4位の北海道(5.2%)までが5%台の上昇率です。すごい上昇していますね。
全国の最高路線価はおなじみですが、「東京都中央区銀座5丁目」(鳩居堂前)で1㎡当たり4424万円(前年比1.04上昇)、39年連続で最高値となりました。過去の全国最高額は2020年の4592万円でしたので、コロナで地価が下がっていたともいえます。
鳩居堂に続く路線価は、大阪・御堂筋の2024万円(同5.4%上昇)、3位が横浜・横浜駅西口バスターミナル前通りで1696万円(同1.0%上昇)、4位が名古屋・名駅1丁目名駅通りで1288万円(同0.6%上昇)、5位が福岡・天神2丁目渡辺通りで944万円(同4.4%上昇)でした。
対前年との変動率を見ると、最も上昇した都市は、千葉市中央区富士見2丁目千葉駅東口駅前広場で14.9%上昇(223万円)、2位がさいたま市大宮区桜木町2丁目大宮西口駅前ロータリーで11.4%上昇(529万円)、3位岡山市北区本町市役所筋で9.1%上昇(179万円)、4位が札幌市中央区北5条西3丁目札幌停車場線通りで9.0%上昇(728万円)、5位が福井市中央1丁目福井駅西口広場前通りで8.6%上昇(38万円)でした。
全国の主要都市で路線価が上昇に向かっているのは、再開発事業が活発化しているエリアであったり、コロナ明けで社会経済活動が正常化するとともに、国内外の観光需要が盛り返し、特に訪日観光客が押し寄せているところで地価を押し上げています。
上昇率が5%以上10%未満の都市は、札幌、福井、京都、大阪、神戸、奈良、岡山、広島の8都市となり、前年から3都市増加しました。
上昇率が5%未満の都市は、盛岡、仙台、秋田、宇都宮、前橋、新潟、長野、東京、横浜、富山、金沢、岐阜、静岡、名古屋、津、大津、和歌山、徳島、高松、松山、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、那覇の27都市となりました。
横ばいの都市は、青森、山形、福島、水戸、甲府、松江、山口、高知、宮崎の9都市です。
神戸も地下上昇しているので今後の土地売却に関しては、期待が持てますね。
見出し:相続税評価額は引き上げとなりました
2024年1月1日以降から不動産の相続税評価額を従来の4割程度から6割以上まで引き上げられました。2022年4月に最高裁判決でタワーマンションなど不動産を購入することで過度な節税を認めず国税当局の追徴課税を適法と認めたことがきっかけとなりました。
国税庁は、いわゆるタワマンを使っての相続税の評価額は、市場で取引される売買価格(時価)との乖離が大きく、富裕層の優遇だとの指摘を受けて、税負担の公平性から判断して新たに算定ルールを導入した。その市場価格と乖離要因となっている「築年数」、「総回数(総階数指数)」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4つの指数に基づいて評価額を補正する結果となり、相続税評価額の引き上げにつながりました。
といってもまだまだ市場の価格には相続税評価は追いついておらず、節税としての役割は担えそうですね。
不動産のご相談は神戸アイランド不動産にお任せください。